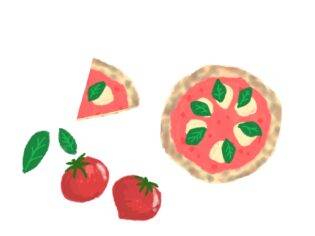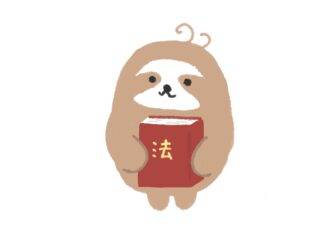9月19日は何の日?何の記念日?。簡単なエピソードとぽんぷーのイラストを添えてご紹介します。ちょっとした雑学ネタとして、何となく知ってたらいつか役に立つかも?
※面白い記念日が認定されたら追加していきます。
全ての国民が名字を持つきっかけとなった日: 苗字の日
1870年(明治3年)のこの日、戸籍整理のため、「平民苗字許可令」という太政官布告により平民も苗字を名乗ることが許された。

Q: なぜ江戸時代まで平民は苗字を名乗れなかったのですか?
A: 江戸幕府は身分制度を確立する中で、武士などの支配階級に特権を与えるため、公の場で苗字を名乗ること(苗字帯刀)を原則として武士だけに許し、農民や町人などの平民には禁止していました。ただし、一部の有力な庄屋や町人などは、特別な許可を得て苗字を名乗ることもありました。
Q: 「平民苗字許可令」が出されて、すぐに皆が苗字を名乗るようになったのですか?
A: いいえ、この布告はあくまで「許可」であり、義務ではありませんでした。また、新たに苗字を名乗ると税金が増えるといった噂も流れ、なかなか普及しませんでした。そのため、1875年(明治8年)には「平民苗字必称義務令」が出され、すべて国民が苗字を名乗ることが義務付けられました。
Q: 日本にはどれくらいの種類の苗字があるのですか?
A: 正確な数は把握されていませんが、一説には10万種類以上とも、30万種類近くあるとも言われ、世界的に見ても非常に多様な苗字が存在します。これは、地名、職業、地形、植物など、様々な由来を持つ苗字が作られてきたためです。
リアス海岸の絶景、語呂合わせでPRする地域の日: 九十九島の日
長崎県佐世保市が1999年(平成11年)に制定。日付は「く(9)じゅうく(19)しま」(九十九島)と読む語呂合わせから。
Q: 九十九島は本当に99の島なのですか?
A: 「九十九」は「非常に数が多い」ことを意味する表現であり、実際の島の数は208あると言われています。佐世保港の外側から北へ約25kmにわたって、複雑なリアス海岸に無数の島々が点在する美しい景観が広がっています。
Q: 九十九島はどこにありますか? どのような場所ですか?
A: 長崎県佐世保市の北部から平戸市にかけての北松浦半島西岸に連なる群島です。大部分が西海国立公園に指定されており、風光明媚な景観で知られています。展望台からの眺めや、遊覧船での島めぐりが人気です。
Q: 九十九島の他の魅力は何ですか?
A: 美しい夕日が見られることでも有名です。また、複雑な海岸線と栄養豊富な海は、カキ(九十九島かき)やトラフグなどの養殖に適しており、グルメも楽しめます。シーカヤックやヨットなどのマリンスポーツも盛んです。
心の整理もサポート、専門サービスの認知度向上を目指す日: 遺品整理の日
株式会社アヴァックが制定。日付は依頼された遺品の整理をすぐ「クイック=9.19」にするという意味から。
Q: なぜ「クイック」が日付の由来なのですか?
A: 依頼に対して迅速(Quick)に対応するというサービスの姿勢を「クイ(9)ック(19)」という語呂合わせで表現し、遺品整理サービスを提供する株式会社アヴァックが制定しました。
Q: 遺品整理とは具体的にどのようなことをするのですか?
A: 故人が残した品々(遺品)を、遺族に代わって整理・片付けするサービスです。 단순히不用品を処分するだけでなく、貴重品や思い出の品を探し出したり、必要なものと不要なものを仕分けたり、部屋の清掃や不用品の適切な処分(リサイクル、供養、廃棄など)まで行います。
Q: なぜ専門業者に依頼する人が増えているのですか?
A: 遺族が高齢であったり、遠方に住んでいたりして、自分たちで整理するのが難しい場合や、故人の家が賃貸物件で早急に片付ける必要がある場合などが増えています。また、大量の遺品整理は精神的・肉体的な負担が大きいため、専門知識を持つ業者に任せることで、スムーズかつ適切に進められるというメリットがあります。
近代俳句・短歌の革新者、正岡子規を偲ぶ日: 糸瓜忌・獺祭忌
俳人・歌人であり、日本の近代文学に大きな影響を与えた正岡子規(まさおか しき)の命日です(1902年(明治35年)9月19日)。結核を患い、晩年は病床にありながらも創作活動を続けました。
Q: なぜ「糸瓜忌(へちまき)」や「獺祭忌(だっさいき)」と呼ばれるのですか?
A: 子規が亡くなる前日、辞世の句として詠んだとされる「糸瓜咲て痰のつまりし仏かな」「痰一斗糸瓜の水も間にあはず」「をとゝひのへちまの水も取らざりき」の三句にちなんで「糸瓜忌」と呼ばれます。また、「獺祭書屋主人(だっさいしょおくしゅじん)」という雅号(ペンネーム)を用いていたことから「獺祭忌」とも呼ばれます。「獺祭」とは、カワウソ(獺)が捕らえた魚を岸に並べる様子が、多くの書物を広げて参考にしている姿に似ていることに由来します。
Q: 正岡子規は文学にどのような貢献をしましたか?
A: 俳句や短歌において、旧来の月並みな表現を批判し、見たままの情景を客観的に写し取る「写生」を提唱しました。これにより、俳句・短歌の世界に近代的なリアリズムをもたらし、革新を起こしました。俳句雑誌『ホトトギス』の創刊にも関わり、多くの後進を育てました。
Q: 正岡子規ゆかりの場所はありますか?
A: 出身地である愛媛県松山市には、子規記念博物館や、復元された住居「子規堂」があります。晩年を過ごした東京都台東区根岸の住居跡は「子規庵」として保存されており、彼の生活や創作活動の様子を偲ぶことができます。
ヨーホー!海賊になりきって楽しむユーモラスな国際デー: 世界海賊口調日 (International Talk Like a Pirate Day)
毎年9月19日に、「Aye, matey!」や「Shiver me timbers!」といった、いわゆる「海賊のような口調」で一日を過ごそう!というユーモラスな記念日です。1995年にアメリカの友人同士(ジョン・バウアとマーク・サマーズ)が冗談で始めたものが、コラムニストのデイヴ・バリーに取り上げられたことで世界的に広まりました。
Q: なぜこの日が選ばれたのですか?
A: 特に深い意味はなく、提唱者の一人であるマーク・サマーズの元妻の誕生日が、このアイデアが生まれた日(6月6日)では都合が悪かったため、覚えやすい日付として9月19日が選ばれた、という説が有力です。
Q: どのように祝う(楽しむ)日なのですか?
A: 難しく考える必要はなく、一日だけ友人や同僚と海賊っぽい言葉遣い(語尾に「Arrr!」を付けるなど)で会話したり、海賊の仮装(眼帯、帽子、バンダナなど)をしたりして、純粋に楽しむことが目的です。チャリティーイベントなどが開催されることもあります。
Q: いわゆる「海賊口調」はどこから来たのですか?
A: 実際の海賊が使っていた言葉というよりは、小説『宝島』やディズニー映画『パイレーツ・オブ・カリビアン』などのフィクション作品を通じて形成された、ステレオタイプなイメージに基づいています。