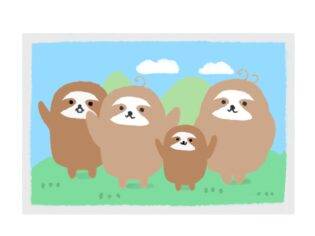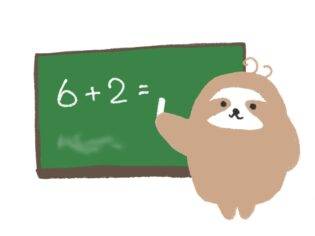10月14日は何の日?何の記念日?。簡単なエピソードとぽんぷーのイラストを添えてご紹介します。ちょっとした雑学ネタとして、何となく知ってたらいつか役に立つかも?
※面白い記念日が認定されたら追加していきます。
世界の円滑な連携を支える: 世界標準の日 (World Standards Day)
国際標準化機構(ISO)と国際電気標準会議(IEC)が、世界の標準化活動を促進するために1960年(昭和35年)に制定。世界標準の策定に貢献した専門家たちに感謝し、その労をねぎらうとともに、標準化が世界経済や社会にもたらす重要性について、産業界や消費者、政府などの意識を高めることを目的としています。
Q: 国際標準とは具体的にどのようなものがありますか?
A: 私たちの身の回りには多くの国際標準があります。例えば、非常口のマーク(ISO 7010)、カードのサイズ(ISO/IEC 7810)、ネジの規格、品質マネジメントシステム(ISO 9001)、情報セキュリティマネジメントシステム(ISO/IEC 27001)などが代表的です。これらは、製品やサービスの品質、安全性、互換性を確保するために役立っています。
Q: なぜ国際標準化が必要なのですか?
A: 国際標準があることで、異なる国やメーカーの製品・サービスでも互換性が保たれ、消費者は安心して利用できます。また、企業にとっては、製品開発や生産の効率化、国際的な貿易の円滑化につながります。さらに、安全性や環境保護に関する基準を設けることで、社会全体の持続可能な発展にも貢献します。
Q: この日は世界でどのように祝われますか?
A: ISOやIEC、そして各国の標準化機関が中心となり、標準化の重要性をテーマにしたセミナー、展示会、ワークショップ、表彰式などを開催します。毎年テーマが設定され、その年の重点課題に関する議論や啓発活動が行われます。
日本の鉄道開業を祝う: 鉄道の日
元々は1922年(大正11年)に当時の鉄道省(後の日本国有鉄道)が「鉄道記念日」として制定しました。日付は、1872年(明治5年)10月14日(旧暦9月12日)に、新橋駅(後の汐留貨物駅、現:廃止)と横浜駅(現:根岸線桜木町駅)の間で日本初の鉄道が正式開業したこと、および1921年(大正10年)の同日に鉄道開業50周年を記念して東京駅丸の内北口に初代の鉄道博物館が開館したことに由来します。

Q: 日本で最初の鉄道はどこを走っていたのですか?
A: 東京の新橋駅(現在の汐留シオサイト付近にあった初代)と、横浜駅(現在のJR桜木町駅)の間、約29kmの区間を走りました。当時の所要時間は約53分だったと記録されています。
Q: なぜ10月14日が「鉄道の日」に選ばれたのですか?
A: 日本の近代化を象徴する出来事であった鉄道の正式開業日であること、そして鉄道開業50周年という節目の年に鉄道博物館が開館した記念すべき日であることが理由です。1994年に「鉄道の日」と名称が変更され、運輸省(現:国土交通省)主導で関連行事が行われるようになりました。
Q: 鉄道の日にはどのようなイベントがありますか?
A: 全国の鉄道事業者や関連団体によって、車両基地の一般公開、記念列車の運行、鉄道グッズの販売、写真展、スタンプラリー、鉄道模型の展示など、様々なイベントが開催されます。特に東京の日比谷公園などで開催される「鉄道フェスティバル」は有名です。
100エーカーの森の物語が始まった日: くまのプーさん原作デビューの日
ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社が制定。日付は、イギリスの作家A.A.ミルンによって書かれ、世界中で愛されている児童小説『くまのプーさん』(Winnie-the-Pooh)の原作が、1926年(大正15年)10月14日にロンドンで初めて出版されたことに由来します。
Q: 原作『くまのプーさん』の作者は誰ですか?
A: イギリスの作家アラン・アレクサンダー・ミルン(A. A. Milne)です。彼は息子のクリストファー・ロビンが持っていたテディベアなどのぬいぐるみから着想を得て、プーさんとその仲間たちが活躍する物語を書きました。挿絵はE.H.シェパードが担当しました。
Q: ディズニーアニメ版と原作の違いは何ですか?
A: ディズニー版は原作の雰囲気を大切にしつつも、より子ども向けにキャラクターデザインやストーリーがアレンジされています。例えば、プーさんの赤いシャツはディズニー版オリジナルです。また、ゴーファーやラビットの友人たちはディズニー版で追加されたキャラクターです。原作は、より詩的で哲学的なユーモアが含まれているとも言われます。
Q: プーさんの名前の由来は何ですか?
A: 「ウィニー(Winnie)」は、当時ロンドン動物園にいた実在の雌の仔熊の名前から取られました。「プー(Pooh)」は、クリストファー・ロビンが好きだった白鳥の名前、または何かにつまずいた時の音など、諸説あります。
ご当地グルメ対決がきっかけ: 焼うどんの日
福岡県北九州市小倉で活動する市民団体「小倉焼うどん研究所」が制定。日付は、2002年(平成14年)10月14日に、静岡県富士宮市のまちおこし団体「富士宮やきそば学会」と、焼うどん・やきそば対決イベント「焼うどんバトル特別編 ~天下分け麺の戦い~」を行い、北九州市小倉が「焼うどん発祥の地」として全国的に知られるきっかけとなったことから。
Q: なぜ小倉が焼うどん発祥の地と言われるのですか?
A: 第二次世界大戦後の食糧難の時代(1945年頃)、小倉の食堂「だるま堂」の主人が、焼きそばを作ろうとした際にそば玉が手に入らず、代わりに干しうどんを使って作ったのが始まりとされています。これが美味しかったことから、他の店にも広まっていったと言われています。
Q: 小倉焼うどんの特徴は何ですか?
A: 発祥とされるだるま堂のスタイルを受け継ぎ、乾麺のうどんを使うのが特徴です。茹でたうどんをキャベツや豚肉などの具材と一緒に炒め、ソースや醤油などで味付けします。仕上げに目玉焼きを乗せることも多いです。お店によって味付けや具材は様々です。
Q: 「天下分け麺の戦い」とはどのようなイベントだったのですか?
A: 当時B級グルメとして人気を博していた「富士宮やきそば」と、発祥の地をアピールし始めた「小倉焼うどん」が、どちらがより魅力的かを競う対決形式のイベントでした。このイベントはメディアにも取り上げられ、小倉焼うどんの知名度向上に大きく貢献しました。