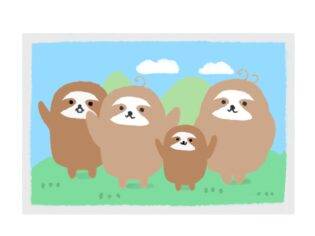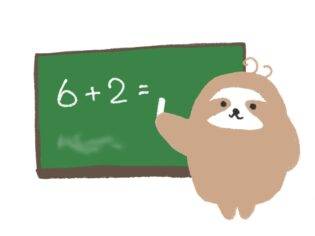10月29日は何の日?何の記念日?。簡単なエピソードとぽんぷーのイラストを添えてご紹介します。ちょっとした雑学ネタとして、何となく知ってたらいつか役に立つかも?
※面白い記念日が認定されたら追加していきます。
戦後復興を願って: 宝くじ発売の日
1945年(昭和20年)10月29日、日本で初めて、政府によって臨時資金調整法に基づいた宝くじ(政府第1回宝籤)が発売されました。これは、終戦直後の厳しい財政状況の中で、戦災からの復興資金を調達することを主な目的としていました。
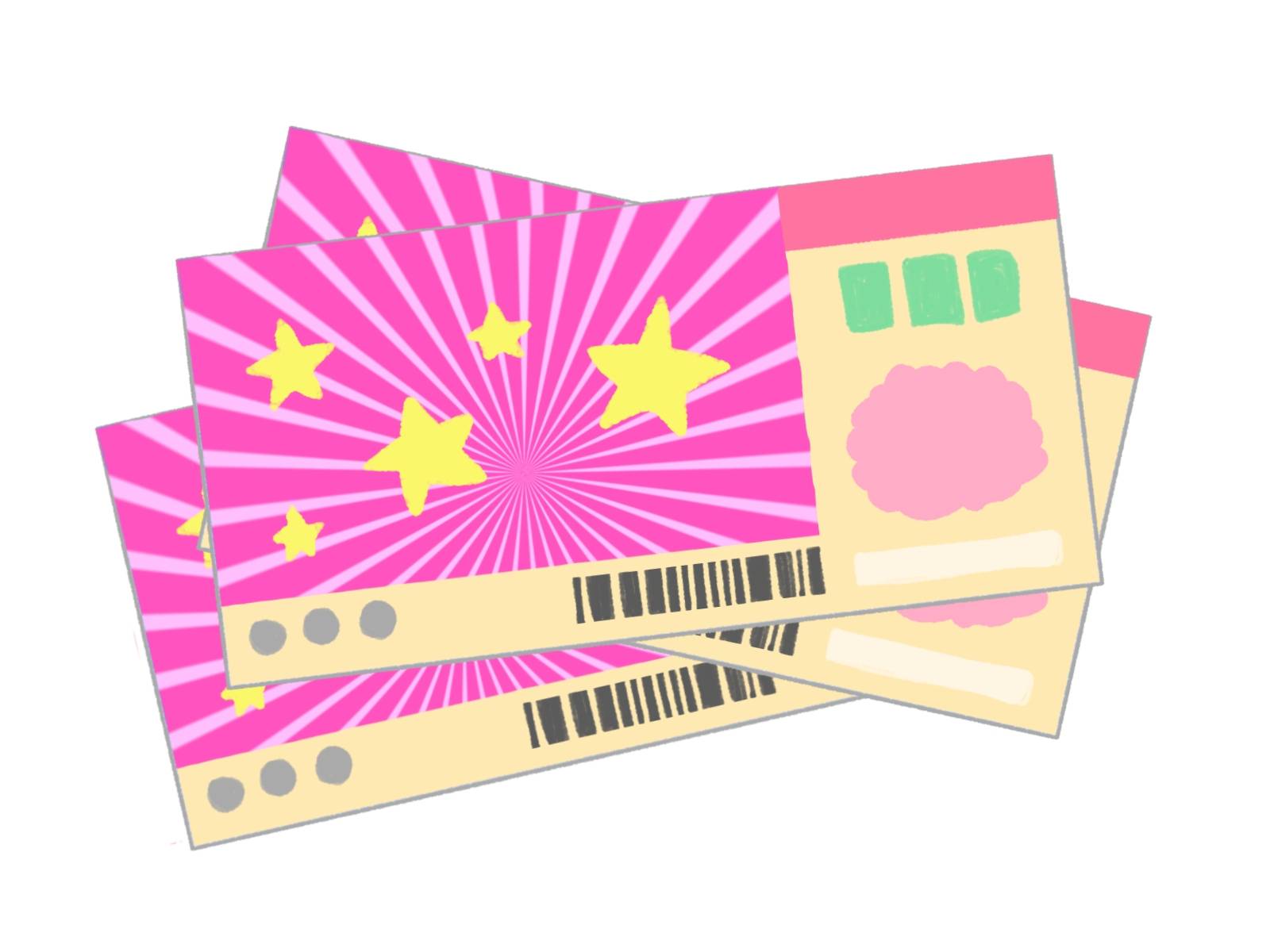
Q: なぜ政府が宝くじを発売したのですか?
A: 終戦直後の日本は、戦争による国土の荒廃と深刻なインフレーションに苦しんでいました。政府は復興に必要な資金を確保するため、国民に夢と希望を与えつつ資金を集める手段として、宝くじを発行することを決定しました。
Q: 当時の宝くじはどのようなものでしたか?
A: 第1回の宝くじは1枚10円で発売され、1等賞金は10万円でした。当時の物価からすると非常に高額であり、多くの人々が一攫千金を夢見て買い求め、発売日には長い行列ができたと言われています。
Q: 宝くじの収益金は何に使われますか?
A: 宝くじの収益金は、発売当初の復興資金だけでなく、現在では法律に基づき、公共事業(道路、橋、公園、学校、福祉施設などの整備)、地方自治体の財源、社会貢献活動などに充てられ、私たちの暮らしに役立てられています。
家庭での映像記録の始まり: ホームビデオ記念日
1969年(昭和44年)10月29日に、ソニー、松下電器(現:パナソニック)、日本ビクター(現:JVCケンウッド)の3社が、世界で初めて家庭用VTR(ビデオテープレコーダー)の統一規格である「U規格」(ユーマチック)を発表したことを記念する日です。
Q: 「U規格」とはどのようなものだったのですか?
A: それまで放送局などで使われていた高価で大型の業務用VTRに対し、一般家庭でも導入できるようなサイズと価格を目指して開発された、カセット式のビデオテープ規格です。幅が3/4インチのテープを使用しました。
Q: U規格の発表はなぜ重要だったのですか?
A: U規格の登場は、テレビ番組を家庭で録画して好きな時に見る(タイムシフト視聴)という、現在のビデオレコーダーや録画機能付きテレビに繋がる文化の幕開けとなりました。映像を個人が所有し、繰り返し見ることが可能になった画期的な出来事でした。
Q: その後の家庭用ビデオ規格はどうなりましたか?
A: U規格は主に教育・業務用として普及しましたが、家庭用としては、より小型で安価な「ベータマックス」(ソニー)と「VHS」(日本ビクター)が登場し、激しい規格争いを繰り広げました。最終的にはVHSが主流となり、その後DVD、Blu-ray、そしてハードディスク録画やネット配信へと技術は進化していきました。
世界を変えた接続: インターネット誕生日
1969年(昭和44年)10月29日、現代のインターネットの原型とされるコンピューターネットワーク「ARPANET」(アーパネット)において、世界で初めて2台のコンピューター間での通信(データ送信)が成功した日です。
Q: ARPANETとはどのようなネットワークでしたか?
A: アメリカ国防総省の高等研究計画局(ARPA、後のDARPA)が、核攻撃などによって一部が破壊されても機能し続ける頑強な通信ネットワークの研究プロジェクトとして開発したものです。当初は、大学や研究機関のコンピューター同士を接続するために使われました。
Q: 世界で最初の通信はどのようなものでしたか?
A: カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)からスタンフォード研究所(SRI)へ、「LOGIN」という文字を送ろうと試みました。まず「L」を送り、電話で相手に届いたか確認。次に「O」を送り、確認。しかし、「G」を送ろうとしたところでシステムがクラッシュしてしまったそうです。不完全ながらも、これが歴史的な最初の通信となりました。
Q: ARPANETはどのように現在のインターネットに進化したのですか?
A: ARPANETで開発されたパケット交換技術やTCP/IPといった通信プロトコル(通信規約)が、後のインターネットの基盤となりました。1980年代には軍事用と研究用にネットワークが分離され、研究用ネットワークが発展して、1990年代のWorld Wide Web(WWW)の登場などにより、世界中の誰もが利用できる現在のインターネットへと進化していきました。
手を拭く日本のおもてなし: おしぼりの日
おしぼりのレンタル・リース業者などで構成される全国おしぼり協同組合連合会(全協連)が2004年(平成16年)に制定。日付は、10月は「て(ten=10)」と読む語呂合わせと10本の指から、29日は「ふ(2)く(9)」(拭く)と読む語呂合わせで、「手を拭く」ことを記念しています。
Q: なぜ「おしぼりの日」が制定されたのですか?
A: 日本独特のおもてなし文化の一つである「おしぼり」の役割や価値を再認識してもらい、その利用促進と衛生意識の向上を図ることを目的としています。おしぼり業界の活性化も目指しています。
Q: おしぼりの文化はいつ頃からあるのですか?
A: その起源は古く、平安時代に公家が客をもてなす際に濡れた布を提供したのが始まりとも言われています。江戸時代には旅籠(宿屋)で旅人の手足を拭くために提供され、明治時代以降、飲食店などで広く使われるようになりました。
Q: おしぼりにはどのような効果がありますか?
A: 手を清潔にする衛生的な効果はもちろん、温かいおしぼりはリラックス効果を、冷たいおしぼりはリフレッシュ効果を与えてくれます。食事の前などに手を拭くことで、気持ちを切り替え、食事をより楽しむための準備ともなります。
冬支度の必需品: てぶくろの日
作業用手袋などを製造・販売する株式会社東和コーポレーション(福岡県久留米市)が制定。日付は「て(10)ぶ(2)く(9)ろ」(手袋)と読む語呂合わせと、寒くなり始め、素手での作業が辛くなり、手袋を使い始める時期であることから。
Q: なぜ東和コーポレーションが制定したのですか?
A: 手袋の専門メーカーとして、様々な用途で使われる手袋の重要性や利便性を広くアピールし、その利用を促進することで、自社製品の販売促進とブランド認知度向上を図る目的があると考えられます。
Q: 「て(10)ぶ(2)く(9)ろ」の語呂合わせについて教えてください。
A: 「て」を数字の「10(テン)」に、「ぶ」を数字の「2(ふたつ)」に、「く」を数字の「9(く)」にかけた、ストレートな語呂合わせです。
Q: 手袋にはどのような種類や役割がありますか?
A: 寒さから手を守る「防寒用手袋」、作業中の怪我や汚れを防ぐ「作業用手袋」(軍手、ゴム手袋、革手袋など)、ファッションの一部としての「おしゃれ手袋」、スポーツ用の「グローブ」、医療用の「使い捨て手袋」など、目的や用途に応じて様々な種類があります。手を保護し、作業効率を高め、快適さを提供する役割があります。
ホテル発祥の洋食メニュー: ドリアの日
横浜にある老舗ホテル、株式会社ホテル、ニューグランドが制定。日付は、同ホテルの初代総料理長であり、日本にドリアを伝えたとされるスイス人シェフ、サリー・ワイル(Saly Weil)が来日した1927年(昭和2年)10月29日に由来します。
Q: なぜホテルニューグランドが制定したのですか?
A: ドリア発祥の地とされる同ホテルが、その歴史的な功績と料理の魅力を広く伝え、ホテルブランドの価値を高めるために制定したと考えられます。日本で生まれた人気の洋食メニューの誕生日を祝う意味合いもあります。
Q: ドリアはどのようにして生まれたのですか?
A: ホテルニューグランドに滞在していた銀行家から「体調が良くないので、何かのど越しの良いものを」とリクエストされた際に、初代総料理長のサリー・ワイルが即興で考案した料理とされています。ピラフ(またはバターライス)の上にエビなどの魚介クリームソースとチーズをかけてオーブンで焼いたものが最初だったと言われています。
Q: ドリアとグラタンの違いは何ですか?
A: 一般的に、グラタンはマカロニやジャガイモなどの具材にホワイトソースやチーズをかけて焼いた料理を指します。一方、ドリアはご飯(ピラフ、バターライス、白飯など)の上にソースとチーズをかけて焼いた料理を指します。つまり、主食がご飯である点がドリアの大きな特徴です。
世界市民の健康課題: 世界脳卒中デー (World Stroke Day)
世界脳卒中機関(World Stroke Organization, WSO)が制定した国際デーです。脳卒中(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血など)の予防、治療、リハビリテーションに関する意識を世界的に高め、その対策を促進することを目的としています。
Q: なぜ脳卒中の啓発デーが必要なのですか?
A: 脳卒中は、世界的に見て死亡原因の上位を占め、また、深刻な後遺症を残すことが多い病気です。しかし、その多くは高血圧、糖尿病、脂質異常症、心房細動などの危険因子を管理することや、健康的な生活習慣(禁煙、節酒、運動、バランスの取れた食事など)によって予防が可能とされています。早期発見・早期治療も非常に重要です。
Q: 脳卒中の前触れや症状にはどのようなものがありますか?
A: 突然、片方の手足や顔半分の麻痺・しびれ、ろれつが回らない・言葉が出ない、めまい・ふらつき、視野の一部が欠ける、激しい頭痛などが代表的な症状です。「FAST」(Face:顔の歪み, Arm:腕の麻痺, Speech:言葉の障害, Time:発症時刻を確認しすぐ救急車)という標語で、迅速な対応の重要性が啓発されています。
Q: この日にはどのような活動が行われますか?
A: 世界各地で、脳卒中の予防や症状に関する啓発キャンペーン、講演会、健康診断、ウォーキングイベントなどが開催されます。医療機関や関連学会、患者団体などが中心となって活動を展開しています。
トルコ国民の祝日: トルコ共和国建国記念日
1923年10月29日に、ムスタファ・ケマル・アタテュルク(Mustafa Kemal Atatürk)がトルコ共和国の樹立を宣言し、初代大統領に就任したことを記念する、トルコの最も重要な国民の祝日です。これにより、オスマン帝国は名実ともに終焉を迎え、政教分離を原則とする近代的な共和国が誕生しました。
Q: なぜオスマン帝国からトルコ共和国になったのですか?
A: 第一次世界大戦に敗北し、存亡の危機にあったオスマン帝国において、ムスタファ・ケマルを中心とするトルコ民族主義者たちが祖国解放戦争(トルコ独立戦争)を戦い抜き、外国勢力を排除しました。その後、スルタン制(皇帝制)を廃止し、国民が主権を持つ共和国体制を樹立しました。
Q: ムスタファ・ケマル・アタテュルクはどのような人物ですか?
A: トルコ共和国の建国の父であり、初代大統領です。「アタテュルク」は「トルコ人の父」を意味する姓で、議会から贈られました。彼は、政教分離、ローマ字の採用、女性参政権の導入など、トルコを近代的な世俗国家へと導くための大胆な改革を次々と断行しました。
Q: トルコではどのように祝われますか?
A: 首都アンカラをはじめ、全国各地で盛大な式典、軍事パレード、コンサート、花火などが催されます。学校や官公庁は休みとなり、街中にはトルコ国旗が掲げられ、国民全体で共和国の誕生日を祝います。