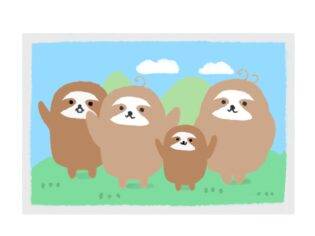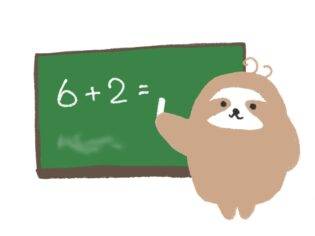10月15日は何の日?何の記念日?。簡単なエピソードとぽんぷーのイラストを添えてご紹介します。ちょっとした雑学ネタとして、何となく知ってたらいつか役に立つかも?
※面白い記念日が認定されたら追加していきます。
感謝を込めて人形を供養: 人形の日
日本人形協会と日本玩具及び人形連盟が1965年(昭和40年)に制定。この日には全国各地の神社などで、古くなったり壊れたりした人形を供養する「人形供養」や、人形への感謝を示す「人形感謝祭」などが開催されます。
Q: なぜ人形の記念日が制定されたのですか?
A: 子どもたちの成長を見守り、遊び相手となってくれた人形への感謝の気持ちを表し、物を大切にする心を育むことを目的としています。また、日本の伝統的な人形文化の振興も目指しています。
Q: 人形供養はどのような意味があるのですか?
A: 日本では古くから、人形には持ち主の魂が宿ると考えられてきました。そのため、不要になった人形を単にゴミとして処分するのではなく、神社やお寺で供養(読経など)を行い、感謝の気持ちとともに清めてからお別れをするという習慣があります。
Q: 10月15日が選ばれた理由は何ですか?
A: 特定の歴史的出来事に由来するわけではありませんが、秋の人形シーズン(七五三など)を前に、人形への関心を高めるのに適した時期として選ばれた可能性があります。また、各地で行われる人形供養の日程と関連付けられたのかもしれません。
秋の味覚の代表格をPR: きのこの日
きのこ類の生産・流通関係者で組織される日本特用林産振興会が1995年(平成7年)に制定。日付は、10月がきのこの需要が高まる月であり、その月の真ん中の15日が、消費者に対してきのこの栄養価や美味しさを落ち着いてアピールしやすいと考えられたことから選ばれました。

Q: なぜ10月はきのこの需要が高まるのですか?
A: 秋はしいたけ、まいたけ、しめじ、えのきたけ、エリンギなど、多くの種類のきのこが旬を迎え、市場に豊富に出回る季節です。また、鍋物や炊き込みご飯など、きのこを使った温かい料理が美味しく感じられる季節でもあるため、消費量が増える傾向にあります。
Q: きのこにはどのような健康効果がありますか?
A: きのこ類は低カロリーでありながら、食物繊維が豊富に含まれており、腸内環境を整える効果が期待できます。また、免疫力を高めるとされるβ-グルカンや、骨の健康に役立つビタミンD(特に日光に当てた場合)、ビタミンB群、ミネラルなども含んでいます。
Q: 美味しいきのこを選ぶポイントは?
A: 種類によって異なりますが、一般的には、カサが開きすぎておらず、軸が太くしっかりしているもの、傷や変色がないものを選ぶと良いでしょう。しいたけはカサの裏側が白いもの、えのきたけは全体的に白くハリがあるものが新鮮です。
和装の足元を彩る: ぞうりの日
草履(ぞうり)を製造・販売する事業者などで構成される草履興業組合が制定。日付は、七五三(11月15日)や正月など、和装で草履を履く機会が多いシーズンを前に、その需要喚起とPRを行うのに適した時期であることから選ばれました。(具体的な日付の由来は不明瞭な部分もあります)
Q: なぜ「ぞうりの日」が制定されたのですか?
A: 日本の伝統的な履物である草履の文化を継承し、その良さを再認識してもらうとともに、和装の機会が増える時期に合わせて消費を促進することを目的としています。
Q: 草履と下駄の違いは何ですか?
A: 主な違いは底の形状です。草履は底が平らで、革や布、ビニールなどの素材で作られることが多いです。一方、下駄は木製の台に「歯」と呼ばれる突起が付いているのが特徴です。一般的に草履はよりフォーマルな場面で、下駄は浴衣などカジュアルな場面で履かれます。
Q: 草履を選ぶ際のポイントは?
A: 履く着物や場面(フォーマルかカジュアルか)に合わせて、素材やデザイン、鼻緒の色柄を選びます。サイズは、かかとが台から少し(1cm程度)はみ出るくらいが、歩きやすく美しいとされています。鼻緒がきつすぎないか、試着して確認することも大切です。
奇妙なアンモナイト発見を記念: 化石の日
日本古生物学会が2017年に制定。日付は、異常な巻き方で有名なアンモナイトの一種「ニッポニテス・ミラビリス(Nipponites mirabilis)」が、矢部長克博士によって新種として論文に記載・報告された1904年(明治37年)10月15日に由来します。
Q: なぜ「化石の日」が制定されたのですか?
A: 化石や古生物学への関心を高め、その学術的な重要性や面白さを広く一般の人々にも知ってもらうことを目的としています。地球の歴史や生命の進化について考えるきっかけを提供する日です。
Q: 「ニッポニテス・ミラビリス」はなぜ有名になったのですか?
A: 通常、アンモナイトは平面状に規則正しく巻いているのに対し、ニッポニテスは非常に複雑で不規則な立体的な巻き方をしています。その奇妙で美しい形状から「異常巻きアンモナイト」の代表とされ、発見当初はその巻き方の規則性が理解できず、「驚異の(mirabilis)日本の石(Nipponites)」と名付けられました。後にその巻き方にも一定の法則があることが解明されました。
Q: 化石は私たちに何を教えてくれますか?
A: 化石は、過去に生きていた生物の姿や生活、当時の地球環境、生命の進化の歴史などを知るための貴重な手がかりです。地層に含まれる化石を調べることで、地層が堆積した年代や環境を推定することもできます。
正しい手洗いで感染予防: 世界手洗いの日 (Global Handwashing Day)
国際衛生年であった2008年に、ユニセフ(国連児童基金)などが中心となって制定された国際的なキャンペーンデーです。感染症予防の最も効果的な方法の一つである「石けんを使った正しい手洗い」を世界中に広めることを目的としています。
Q: なぜ手洗いがそんなに重要なのですか?
A: 私たちの手には、目に見えない多くの細菌やウイルスが付着しています。その手で口や鼻、目などに触れることで、体内に病原体が侵入し、感染症(風邪、インフルエンザ、感染性胃腸炎、新型コロナウイルス感染症など)を引き起こす原因となります。石けんを使った正しい手洗いは、これらの病原体を効果的に除去することができます。
Q: 正しい手洗いのポイントは何ですか?
A: 流水で手を濡らした後、石けんを十分に泡立て、手のひら、手の甲、指の間、指先(爪の間)、親指の周り、手首まで、全体を丁寧に洗います(目安は30秒程度)。その後、流水で石けんを十分に洗い流し、清潔なタオルやペーパータオルで水気をしっかり拭き取ることが重要です。
Q: 特に手洗いが必要なタイミングはいつですか?
A: 外出から帰った時、トイレの後、咳やくしゃみを手で押さえた後、食事の前後、調理の前後、病気の人をケアした後、動物に触れた後などは、特に意識して手洗いを行うことが推奨されます。
支え合いの心を育む: たすけあいの日
全国社会福祉協議会が1965年(昭和40年)に制定。日常生活での助け合いや、地域福祉活動への参加を呼びかけ、支え合いの心を育むことを目的としています。
Q: なぜこの日が「たすけあいの日」とされたのですか?
A: 制定された具体的な経緯や日付の由来は明確ではありませんが、社会福祉への関心を高め、国民一人ひとりが地域社会の中で互いに助け合うことの重要性を考えるきっかけとするために設けられたと考えられます。
Q: 「たすけあい」にはどのような形がありますか?
A: 日常生活における近隣住民同士の声かけや見守り、高齢者や障害のある人へのちょっとした手伝い、子育て中の家庭へのサポート、災害時のボランティア活動、社会福祉協議会などが実施する地域福祉活動への参加や寄付など、様々な形があります。
Q: なぜ今、たすけあいが必要とされているのですか?
A: 少子高齢化や核家族化、地域社会のつながりの希薄化が進む中で、孤立や生活上の困難を抱える人が増えています。公的な福祉サービスだけでは対応しきれない課題も多く、地域住民一人ひとりの支え合いの力がますます重要になっています。