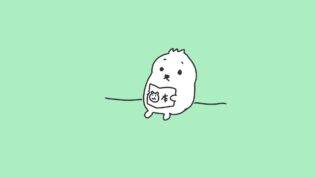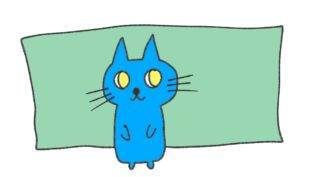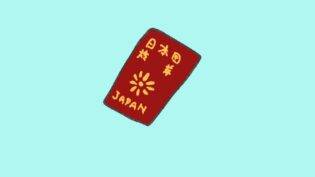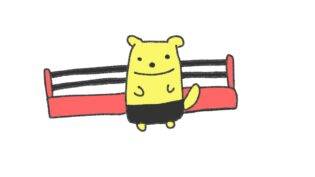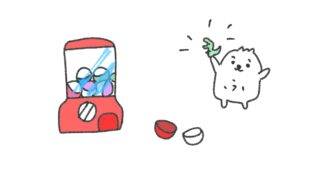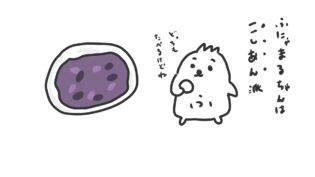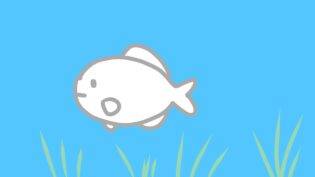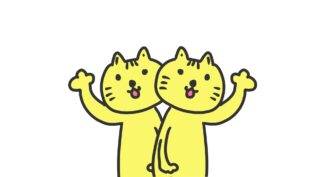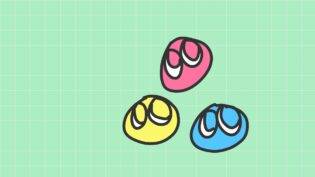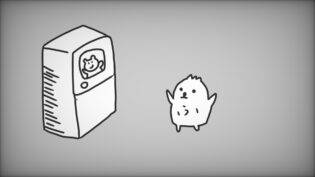2月11日は何の日?何の記念日?。簡単なエピソードとぽんぷーのイラストを添えてご紹介します。ちょっとした雑学ネタとして、何となく知ってたらいつか役に立つかも?
※面白い記念日が認定されたら追加していきます。
国の成り立ちを祝う国民の祝日: 建国記念の日
1966年(昭和41年)の「国民の祝日に関する法律」(祝日法)改正により、「建国をしのび、国を愛する心を養う」ことを趣旨として国民の祝日に制定され、翌1967年(昭和42年)から実施されています。
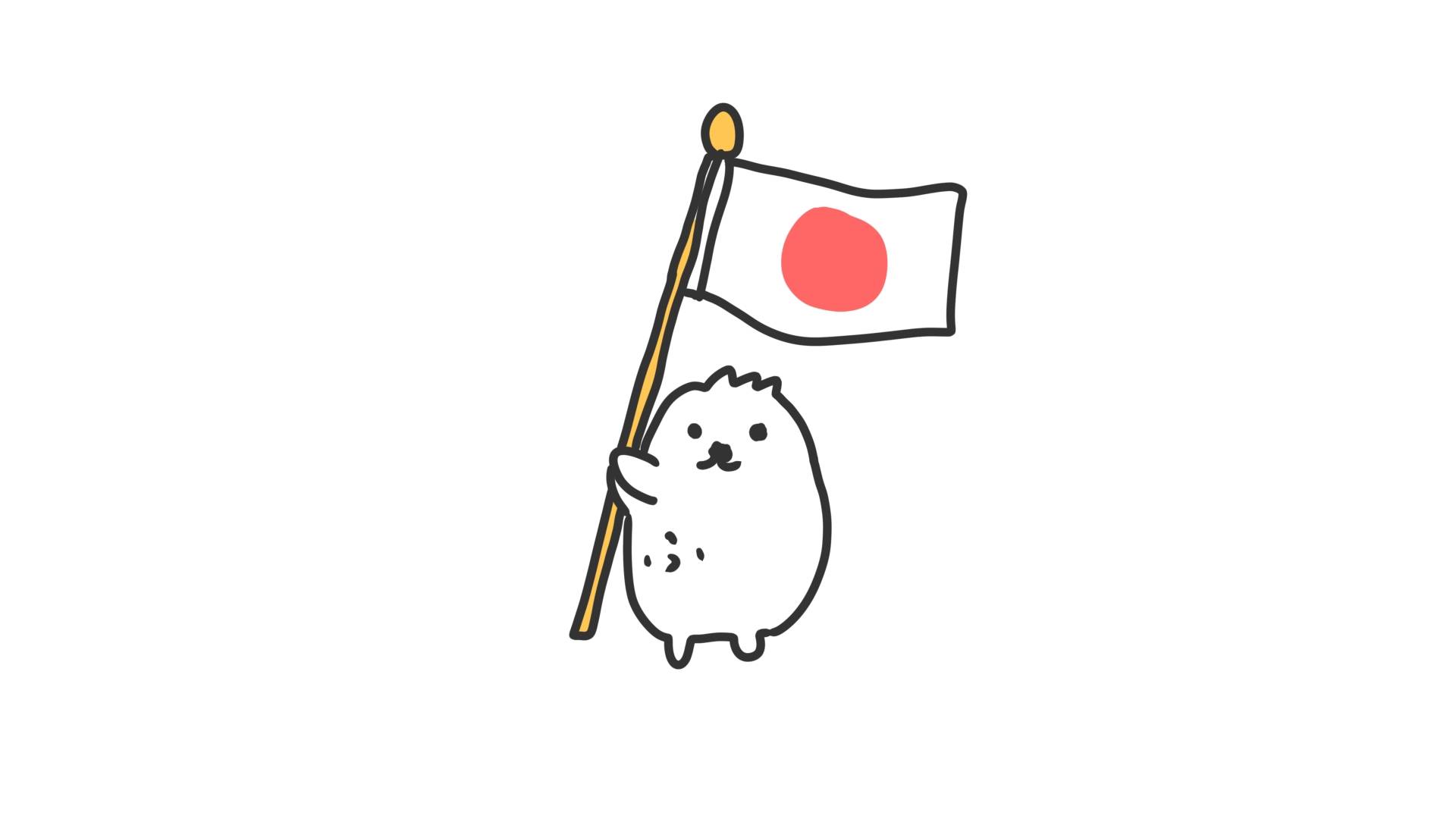
Q: なぜ2月11日が建国記念の日なのですか?
A: 日本の初代天皇とされる神武天皇が即位したとされる日(『日本書紀』によれば紀元前660年の旧暦1月1日)を、明治時代に太陽暦(新暦)に換算した日付が2月11日であるため、この日は戦前「紀元節」という祝祭日でした。戦後、紀元節はGHQの意向等により廃止されましたが、その後、国民の祝日を定めるにあたり、この日付を「建国記念の日」として1966年に制定、翌年から施行されました。
Q: 「建国記念日」ではなく「建国記念の日」なのはなぜですか?
A: 「建国記念日」とすると、歴史的に実際の建国年月日が明確である記念日という意味合いになります。しかし、神武天皇の即位は神話・伝承に基づくものであり、史実としての建国年月日が特定されているわけではないため、「建国されたという事柄そのものを記念する日」という意味を込めて、「の」を入れた「建国記念の日」という名称になりました。
Q: この日にはどのような行事が行われますか?
A: 全国の神社で「建国祭」などの祭典が行われるほか、政府主催の記念式典も開催されます。また、各地で建国を祝う奉祝行事や講演会、パレードなどが行われることもあります。祝日であるため、家庭で国旗を掲揚する習慣も見られます。
祝意を示す国民的慣習が生まれた日: 万歳三唱の日
1889年(明治22年)2月11日、大日本帝国憲法発布の祝賀式典の際、帝国大学(現・東京大学)の学生たちが青山練兵場での観兵式に向かう明治天皇の馬車に向かって、初めて「万歳」を三唱したとされることに由来します。
Q: なぜ学生たちは「万歳三唱」を行ったのですか?
A: 当時、憲法発布という国家的な慶事を祝うにあたり、従来の礼法に代わる新しい表現方法を模索していたようです。教育者らが発案し、学生たちが実行したとされ、「天皇陛下万歳、万歳、万歳」と叫んだのが始まりと言われています。これがきっかけとなり、祝意を表す際の国民的な慣習として広まっていきました。
Q: 「万歳」という言葉の由来は何ですか?
A: もともとは古代中国で皇帝の長寿を祈る言葉(千秋万歳など)として使われていました。「万歳」は文字通り「一万年」を意味し、転じて「永遠の命」「非常に長い年月」を表します。日本では、めでたい時や喜び、祝福の気持ちを表す感動詞として使われるようになり、特に三度繰り返すことで最大限の祝意を示す形式となりました。
文化発展への功労を称える栄典が生まれた日: 文化勲章制定記念日
1937年(昭和12年)2月11日の紀元節に、文化の発達に関する勲章として「文化勲章」が制定されたことを記念する日です。親授式(天皇陛下から直接授与される式典)は、毎年11月3日の「文化の日」に皇居宮殿松の間で行われます。
Q: 文化勲章とはどのようなものですか?
A: 科学技術や芸術など、日本の文化の向上発達に関し特に顕著な功績のあった人に対して授与される、日本の最高位の勲章の一つです。受章者の選考は、文化功労者の中から行われることが原則とされています。
Q: 制定の背景には何があったのですか?
A: 当時の国際情勢の中で、日本の文化の独自性と水準の高さを国内外に示すとともに、文化振興を国家として奨励する目的があったと考えられています。制定日が紀元節(現在の建国記念の日)であることからも、国家的な意義付けがうかがえます。
Q: どのような分野の人が受章していますか?
A: 物理学、化学、医学・生物学などの科学分野、文学、美術(日本画、洋画、彫刻など)、工芸、音楽、演劇、舞踊、建築など、非常に幅広い分野の第一人者が受章しています。ノーベル賞受賞者が後に文化勲章を受章するケースも多く見られます。
一年間の感謝を込めて役目を終えた干支置物を還す日: 干支供養の日
一年間、家や家族を見守り、厄除けや縁起をもたらしてくれた干支の置物に感謝し、供養して元の土に還すという趣旨の日です。岐阜県高山市の「飛騨開運乃森 大七福神」が1989年(平成元年)より提唱し、毎年2月11日午前11時に「干支供養祭」を実施しています。
Q: なぜ干支の置物を供養するのですか?
A: 日本には古くから、長く使った道具や人形などに魂が宿ると考え、大切に扱い、役目を終えた際には感謝を込めて供養するという文化があります(針供養、人形供養など)。干支の置物も同様に、一年間の感謝を示し、単にゴミとして処分するのではなく、敬意をもって自然に還すという考え方に基づいています。
Q: 干支供養祭では具体的にどのようなことが行われますか?
A: 全国の家庭などから送られてきた、その年の前年までの役目を終えた干支の置物を祭壇に集め、神職による祈祷やお祓いが行われます。その後、感謝の気持ちを込めてお焚き上げなどにより、天(自然)に還す儀式が執り行われます。
Q: 干支の置物はいつまで飾っておくのが良いのでしょうか?
A: 特に決まりはありませんが、一般的には新年の縁起物として年末から飾り始め、松の内(1月7日または15日)まで、あるいは節分(2月3日頃)まで飾るという考え方があります。一方で、一年間ずっと飾っておき、次の年の干支の置物と交代する際に古いものを納めるという家庭も多くあります。
銀粒でお馴染みの口中清涼剤の企業が歩み始めた日: 仁丹の日
創業者の森下博が薬種商として独立開業した1893年(明治26年)2月11日と、同社の看板商品である口中清涼剤「仁丹」が発売された1905年(明治38年)2月11日という、二つの重要な日が重なったことを記念して、森下仁丹株式会社が制定しました。
Q: 「仁丹」はどのような製品ですか?なぜ長く愛されているのですか?
A: 桂皮(シナモン)、甘草、阿仙薬(アセンヤク)、生姜など十数種類の生薬を配合し、銀箔でコーティングした小さな粒状の口中清涼剤です。独特の風味と清涼感があり、口臭予防や気分転換、二日酔い対策などに用いられてきました。100年以上にわたる歴史を持ち、特徴的なパッケージデザイン(大礼服マーク)と共に、多くの人に親しまれています。生薬配合による効能感と、携帯しやすい手軽さが長く支持される理由と考えられます。
Q: 仁丹のトレードマーク「大礼服マーク」にはどんな意味がありますか?
A: パッケージに描かれている軍服のような服装の男性マークは、創業者の森下博が日清戦争に従軍した経験から、「国民の健康を守ることは、国に報いること(保健報国)」という理念を持つようになり、その象徴として考案されたと言われています。モチーフは外交官などが着用する大礼服であり、製品の信頼性や品質の高さを表現しているとされます。