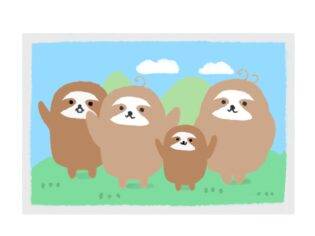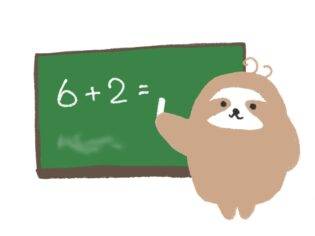10月1日は何の日?何の記念日?。簡単なエピソードとぽんぷーのイラストを添えてご紹介します。ちょっとした雑学ネタとして、何となく知ってたらいつか役に立つかも?
※面白い記念日が認定されたら追加していきます。
コーヒー年度の始まり: 国際コーヒーの日・コーヒーの日
一般社団法人・全日本コーヒー協会が1983年(昭和58年)に「コーヒーの日」を制定。日付は国際協定によって定められた「コーヒー年度」の始まりの日であることから。

Q: なぜ10月1日が「コーヒーの日」なのですか?
A: 国際コーヒー協定によって定められた「コーヒー年度」が10月1日から始まるためです。多くのコーヒー生産国にとって収穫期の始まりとも重なることから、この日が選ばれました。日本では秋冬期にコーヒーの需要が高まることも理由の一つとされています。
Q: 「国際コーヒーの日」も同じ日ですか?
A: はい、国際コーヒー機関(ICO)によって2015年に10月1日が「国際コーヒーの日(International Coffee Day)」と定められました。世界中のコーヒー愛好家がコーヒーを祝い、コーヒー産業が直面する課題への意識を高める日とされています。
秀吉の大茶会にちなんで: 日本茶の日
株式会社伊藤園が制定。日付は天正15年(1587年)10月1日、豊臣秀吉が京都府京都市にある北野天満宮の境内、北野松原で大規模な茶会(北野大茶湯)を開催した故事に由来する。
Q: なぜ伊藤園が「日本茶の日」を制定したのですか?
A: 日本茶の文化や魅力をより多くの人に伝え、消費を促進することを目的として制定されました。伊藤園は日本を代表する茶製品メーカーの一つとして、その普及に貢献したいという思いがあると考えられます。
Q: 北野大茶湯とはどのような茶会だったのですか?
A: 身分に関係なく、茶道具を持っていれば誰でも参加できるという、非常に大規模で画期的な茶会でした。秀吉自身も名だたる茶道具を披露し、日本の茶道文化において重要な出来事とされています。
酒造年度のスタート: 日本酒の日
1978年(昭和53年)に日本酒造組合中央会が、日本酒離れを食い止めるために制定。明治初期に制定された酒造年度(Brewery Year, BY)が10月1日に始まることなどからこの日が選ばれた。

Q: 酒造年度が10月1日に始まるのはなぜですか?
A: 新米が収穫され、酒造りに適した気候になる秋から酒造りが本格化するため、10月1日が新しい酒造りの年度の始まりとされました。これは会計年度などとは異なる、酒造業界独自の年度区分です。
Q: 日本酒の日はどのように祝われますか?
A: 全国の酒造メーカーや販売店、飲食店などで、日本酒の試飲会や割引キャンペーン、日本酒に関するセミナーなどのイベントが開催されることが多いです。日本酒の美味しさや文化に触れる良い機会となっています。
Q: 「日本酒離れを食い止めるため」とは具体的にどういうことですか?
A: 制定された1970年代後半は、洋酒や他のアルコール飲料の消費が増え、伝統的な日本酒の消費量が減少傾向にありました。そこで、日本酒の良さを再認識してもらい、需要を喚起する目的でこの記念日が設けられました。
数字がメガネの形に見える: メガネの日
日本眼鏡関連団体協議会(日眼協)が1997年(平成9年)に制定。日付は10月1日が「1001」と表記でき、「1」をメガネのつる、「0」をレンズとみなすとメガネの形をしていることから。

Q: メガネの日はどのような目的で制定されましたか?
A: メガネに対する正しい知識の普及と、視力矯正だけでなくファッションアイテムとしてのメガネの魅力を広めることを目的としています。また、メガネ業界全体の活性化も目指しています。
Q: この日に関連するイベントはありますか?
A: 全国の眼鏡店で割引セールやフレームの特別展示、視力測定キャンペーンなどが実施されることがあります。また、SNSなどで「#メガネの日」をつけてメガネに関する投稿をする人も見られます。
フランスの香水発売日に合わせて: 香水の日
セフォラ・エーエーピー・ジャパンが2000年(平成12年)に制定。また、日本フレグランス協会も制定。日付はフランスでは新しい香水の発売日が毎年10月1日頃であることから。
Q: なぜフランスの習慣に合わせて制定されたのですか?
A: フランスは香水の文化が深く根付いており、世界の香水市場においても重要な位置を占めています。そのフランスでの慣習に倣うことで、日本でも香水文化を盛り上げ、新しい香りのシーズン到来を祝う意味合いがあると考えられます。
Q: 日本フレグランス協会も制定しているのはなぜですか?
A: 日本フレグランス協会は、日本における香水・フレグランス文化の向上と発展を目指す団体です。香水の魅力を広め、市場を活性化させるために、この記念日を共同で制定・推進していると考えられます。
干支の「酉」と醤油の文字から: 醤油の日
2003年(平成15年)に日本醤油協会など醤油関連団体が制定。「10」が干支で「酉(とり)」にあたり、酉が瓶(かめ)に由来する象形文字であることと、「醤油」という語に「酉」が含まれることから。
Q: 「酉」が瓶(かめ)に由来するとはどういう意味ですか?
A: 十二支の「酉」の字は、もともとお酒や調味料を入れるための瓶(かめ)の形を表した象形文字とされています。醤油も醸造して作られる液体調味料であることから、この「酉」と関連付けられました。
Q: 醤油の日にはどのような活動が行われますか?
A: 醤油メーカーによる工場見学や醤油搾り体験、醤油を使った料理教室、新製品の発表やキャンペーンなどが行われることがあります。日本の食文化に欠かせない醤油の魅力を再発見する日とされています。
「トン(10)カツ(1)」の語呂合わせ: トンカツの日
株式会社「味のちぬや」が制定。日付は10と1で「トン(10)カツ(勝つ=1番)」と読む語呂合わせから。
Q: なぜ「味のちぬや」が制定したのですか?
A: 株式会社「味のちぬや」は冷凍食品メーカーで、トンカツなどのフライ製品も製造・販売しています。自社製品のPRと、日本の食卓で人気の高いトンカツをより楽しんでもらうことを目的に制定したと考えられます。
Q: 「カツ(勝つ=1番)」の解釈は一般的ですか?
A: 「カツ」を「勝つ」にかけて縁起を担ぐのは、受験や試合前などに「カツ丼」や「カツカレー」を食べる習慣として広く知られています。この記念日では、さらに「1(イチ番)」を加えて、より強い勝利への願いやNo.1を目指す意気込みを表現しているユニークな語呂合わせです。
デザイン振興政策スタートの日: デザインの日
1990年(平成2年)に通商産業省(現在の経済産業省)等が制定。1959年(昭和34年)のこの日、デザイン奨励審議会が設置され、デザイン振興政策が本格的にスタートした。デザインに対する理解を深める日。
Q: デザイン奨励審議会とは何ですか?
A: 日本のデザイン水準の向上と、産業や生活におけるデザインの活用を促進するために設置された政府の諮問機関です。デザインの重要性を認識し、国として振興策を進めるきっかけとなりました。
Q: 「デザインの日」には何が行われますか?
A: デザインに関するシンポジウムや展示会、デザイン賞の発表などが行われることがあります。また、企業や教育機関などでデザインの役割や価値について考える機会が設けられることもあります。
東京市が自治権を得た日: 東京都民の日
東京都が1952年(昭和27年)に「都民の日」として制定。1898年(明治31年)のこの日、それまで明治政府の全面的指導下の特別市だったものが、自治権を持つ一般の市になり、市役所が設置された。これにより、東京市が誕生し、1952年までは「東京市自治記念日」であった。
Q: なぜ「東京都民の日」が制定されたのですか?
A: 東京が自治都市として歩み始めた歴史的な日を記念し、都民が郷土(東京)の発展と自身の生活向上を考える日とするためです。また、都政への理解と関心を深める目的もあります。
Q: 都民の日には何か特典がありますか?
A: 都立の動物園、庭園、美術館、博物館などの施設が入場無料になったり、記念行事が開催されたりします。学校が休みになる地域もあります(ただし、近年は実施しない学校も増えています)。
季節の変わり目の習慣: 衣替えの日
季節の変化に応じて衣服を着替える日。明治以降、官庁・学校・企業など制服を着るところでは6月1日と10月1日を「衣替えの日」としているところが多い。
Q: なぜ10月1日が衣替えの日なのですか?
A: 暦の上で秋が深まり、気候が涼しくなる時期であるため、夏服から冬服(または合服)へ移行する目安とされています。平安時代の宮中行事に由来するとも言われていますが、現在のように一斉に行われるようになったのは明治時代以降です。
Q: 衣替えは日本だけの習慣ですか?
A: 四季がはっきりしている日本では広く行われる習慣ですが、制服の切り替えを一斉に行うような形式は日本特有の文化とも言えます。気候に応じて服装を変えること自体は、他の国でも自然に行われています。
Q: 衣替えのメリットは何ですか?
A: 季節に合った服装をすることで快適に過ごせるだけでなく、衣類の整理や手入れをする良い機会になります。不要な服を処分したり、次のシーズンに向けて準備したりすることで、クローゼットの中もすっきりします。
高齢者の貢献を祝う: 国際高齢者デー
1990年の国連総会で制定された国際デーの一つ。高齢者が社会にもたらす貢献に光を当て、感謝するとともに、高齢者が直面する課題(健康、貧困、差別など)に対する意識を高め、解決策を探ることを目的としています。
Q: なぜ10月1日が選ばれたのですか?
A: 特定の歴史的な出来事に由来するわけではありませんが、国連が国際デーを制定する際に、既存の記念日との重複を避けつつ、適切な日付として10月1日が選ばれたと考えられます。
Q: 世界ではどのようなことが行われますか?
A: 各国政府やNGO、地域コミュニティなどが、高齢者のためのイベント、セミナー、健康診断、文化活動などを実施します。また、メディアを通じて高齢者の権利や福祉に関する情報発信が行われます。
法の支配と基本的人権を考える: 法の日
最高裁判所、検察庁、日本弁護士連合会が1960年(昭和35年)に制定。「法の支配」の精神や、基本的人権の尊重といった司法の理念を国民に広く啓発し、理解を深めてもらうことを目的としています。日付は、1928年(昭和3年)10月1日に陪審法が施行されたことに由来します。
Q: 陪審法とは何ですか?
A: 戦前の日本で、一部の刑事事件において一般市民が裁判官と共に有罪・無罪の判断(評決)に参加する制度を定めた法律です。現在の裁判員制度とは異なりますが、司法に国民が参加する先駆けとなりました。
Q: 法の日にはどのような行事がありますか?
A: 全国の裁判所や弁護士会などで、無料法律相談会、裁判所の見学会、模擬裁判、講演会などが開催されます。法や司法の役割について考える良い機会となります。
印章の重要性を再認識: 印章の日
全日本印章業組合連合会が制定。日本の社会生活において重要な役割を果たしてきた印章(ハンコ)の意義と重要性を再認識し、その文化と技術を守り伝えることを目的としています。日付は、明治6年(1873年)10月1日に太政官布告で「実印」「認印」などを定めた制度が制定されたことに由来します。
Q: なぜ印章が重要とされてきたのですか?
A: 古くから日本では、印章が個人の証明や意思表示の証として、契約書や公的書類などで広く用いられてきました。押印することで、その文書の内容に同意したことを示す重要な役割を担っていました。
Q: 最近は脱ハンコの動きもありますが、印章の日はどうなりますか?
A: デジタル化が進み、ハンコの必要性が問い直される場面も増えていますが、印章業界としては、印章の持つ歴史的・文化的価値や、手彫り印章などの伝統技術の継承を訴え続けています。印章の日は、そうした価値を改めて考える日としての意味合いも持つようになっています。