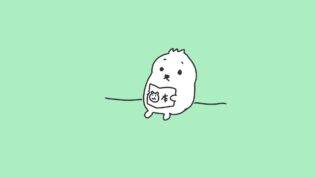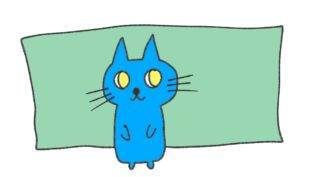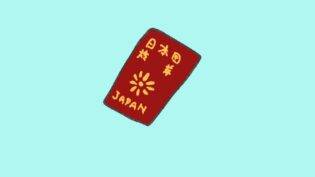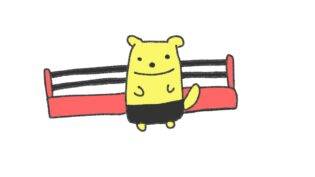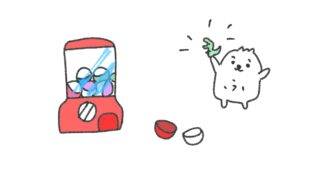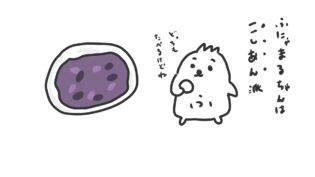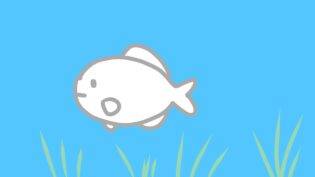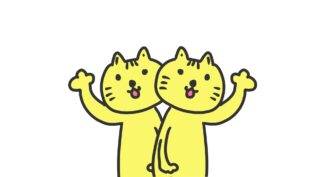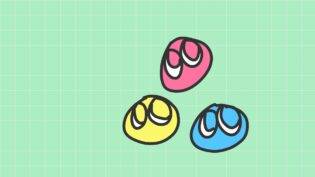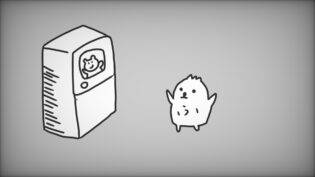2月12日は何の日?何の記念日?。簡単なエピソードとぽんぷーのイラストを添えてご紹介します。ちょっとした雑学ネタとして、何となく知ってたらいつか役に立つかも?
※面白い記念日が認定されたら追加していきます。
日本の食卓に革命を起こした日: ボンカレーの日・レトルトカレーの日
1968年(昭和43年)のこの日、大塚食品工業(現・大塚食品)から世界初の市販用レトルト食品である「ボンカレー」が発売されたことを記念して制定されました。「レトルトカレーの日」とも言われます。
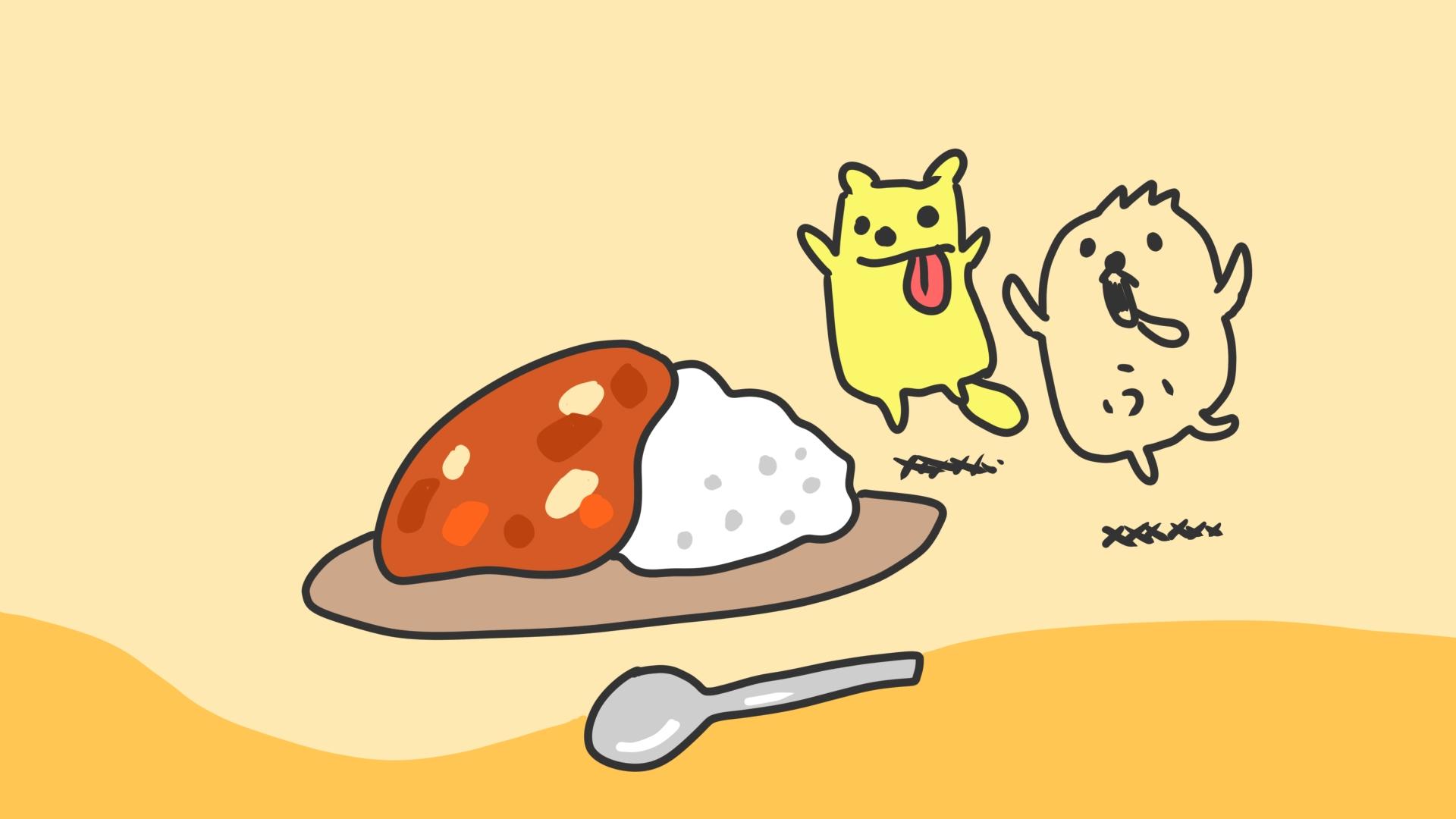
Q: レトルト食品とはどのような技術ですか?
A: 調理済みの食品を、光や空気を遮断する気密性の高いパウチ(袋)や容器に入れ、密封した後に高温高圧で加熱殺菌(レトルト殺菌)する技術です。これにより、常温での長期保存が可能となり、温めるだけですぐに食べられる手軽さが実現しました。この技術はもともとアメリカで軍用食や宇宙食のために開発されたものです。
Q: 「ボンカレー」という名前の由来は何ですか?
A: フランス語で「良い、美味しい」を意味する「Bon」と、英語の「Curry」を組み合わせた造語です。「美味しいカレー」という意味が込められています。
Q: 発売当初の反響はどうでしたか?
A: 発売当初は「お湯で温めるだけでカレーが食べられる」という画期的なコンセプトがすぐには受け入れられず、また当時の物価からするとやや高価(80円)だったこともあり、販売は苦戦しました。しかし、ホーロー看板による宣伝や、有名女優を起用したテレビCM、試食販売などの地道な努力により、徐々にその便利さと美味しさが浸透し、大ヒット商品となりました。
進化論の父、ダーウィンの誕生日: ダーウィンの日
生物進化論の基礎を築いたイギリスの自然科学者、チャールズ・ダーウィンの誕生日(1809年2月12日)を記念する日です。彼の著書『種の起源』(1859年)は、その後の生物学や思想界に計り知れない影響を与えました。
Q: チャールズ・ダーウィンの最も重要な功績は何ですか?
A: ビーグル号での航海を含む長年の観察と研究に基づき、「自然選択説」を中心とした生物進化の理論を提唱したことです。これは、生物は環境に適応するように変化し、生存に有利な形質を持つ個体が子孫を残しやすくなることで種が分岐・進化していくという考え方で、当時の「全ての生物は神によって創造された」という常識を覆すものでした。
Q: 『種の起源』はどのような内容の本ですか?
A: 正式名称は『自然選択による種の起源、あるいは生存闘争における有利な品種の保存について』で、膨大な観察データと考察をもとに、生物が共通の祖先から多様な種へと分岐してきた過程を、主に自然選択のメカニズムによって説明した科学書です。宗教界などからは激しい反発も受けましたが、科学的な議論を巻き起こし、進化という概念を広く浸透させました。
女性のファッションを変えた発明の日: ブラジャーの日(ブラの日)
大手下着メーカーの株式会社ワコールが制定しました。1914年(大正3年)2月12日に、アメリカ人女性メアリー・フェルプス・ジェイコブが、現在のブラジャーの原型となる「バックレス・ブラジャー」の特許を取得したことにちなんでいます。
Q: なぜワコールがこの日を記念日に制定したのですか?
A: ブラジャーの歴史における重要な日を記念することで、女性の美や快適さを支える下着への関心を高め、自社製品のPRにも繋げる目的があると考えられます。ワコールは長年にわたり、女性の体型変化やライフスタイルに合わせたブラジャーの研究・開発を行っています。
Q: メアリー・フェルプス・ジェイコブが発明したブラジャーはどのようなものでしたか?
A: 彼女は当時主流だった鯨の骨などで作られた硬いコルセットの代わりに、薄手のドレスの下に着るために、2枚のハンカチーフとリボン、紐を使って、より軽くて動きやすい下着を考案しました。これが、肩ひもで支え、背中が開いた現代のブラジャーに近い最初の形とされています。
Q: ブラジャーが登場する前は、どのような下着が使われていたのですか?
A: 西洋では、主に胴体を締め付けてバストを持ち上げ、ウエストを細く見せるためのコルセットが長らく用いられていました。しかし、コルセットは窮屈で健康にも悪影響があるとされ、20世紀初頭にはより解放的で機能的な下着が求められるようになっていました。
多くの命を救った奇跡の薬の日: ペニシリンの日
1941年(昭和16年)のこの日、イギリスのオックスフォード大学附属病院の研究チーム(フローリー、チェーンら)が、世界で初めて抗菌薬ペニシリンの人間に対する臨床実験(治療試み)に成功したことを記念する日です。
Q: ペニシリンの発見と臨床実験成功にはどのような意義がありますか?
A: ペニシリンは、細菌感染症に対して劇的な効果を発揮する最初の抗生物質でした。その発見(1928年、アレクサンダー・フレミングによる)と、その後の精製・臨床応用への成功は、それまで治療法がなかった多くの細菌感染症(肺炎、敗血症、梅毒など)から人々の命を救うことを可能にし、医学の歴史を大きく変えました。第二次世界大戦中の負傷兵の治療にも貢献しました。
Q: ペニシリンを発見したのは誰ですか?
A: スコットランドの細菌学者アレクサンダー・フレミングです。彼は1928年、ブドウ球菌の研究中に、実験室のシャーレに生えたアオカビの周囲だけ細菌が生育しないことに偶然気づき、アオカビが細菌を殺す物質(ペニシリン)を産生していることを発見しました。フレミング、フローリー、チェーンの3名はこの功績により1945年にノーベル生理学・医学賞を受賞しました。
Q: 抗生物質とはどのような薬ですか?
A: 微生物(主に細菌)の増殖を抑えたり、殺したりする作用を持つ化学物質のことです。ペニシリンの発見以降、様々な種類の抗生物質が開発され、感染症治療に不可欠な薬剤となっています。ただし、抗生物質の乱用は薬剤耐性菌の出現につながるため、医師の指示に従って適切に使用することが重要です。
黄色の彩りと独特の香りが魅力: 黄ニラ記念日
JA全農おかやま(全国農業協同組合連合会 岡山県本部)が制定しました。日付は「に(2)っこりいい(1)ニ(2)ラ」と読む語呂合わせで、主産地である岡山県の黄ニラをPRすることが目的です。
Q: 黄ニラは普通のニラとどう違うのですか?どのように栽培されるのですか?
A: 黄ニラは、通常の緑色のニラと同じ品種ですが、栽培方法が異なります。日光を遮断するシートなどを被せて育てる「軟白栽培」によって、葉緑素の生成を抑え、黄色く柔らかく育てられます。この特殊な栽培方法により、緑色のニラに比べて香りが穏やかで甘みがあり、シャキシャキとした食感が特徴となります。
Q: 黄ニラの主な産地はどこですか?どのような料理に使われますか?
A: 岡山県が全国一の生産量を誇り、特に岡山市南部の藤田地区などが有名です。高級食材として扱われることが多く、彩りの良さと独特の風味を活かして、お吸い物、炒め物、卵とじ、寿司のネタ(ばら寿司など)といった和食や中華料理によく用いられます。
文豪・司馬遼太郎を偲ぶ日: 菜の花忌
『竜馬がゆく』『坂の上の雲』『燃えよ剣』など数多くの歴史小説で知られる作家・司馬遼太郎(しば りょうたろう)の命日(1996年2月12日)です。彼が菜の花を好んだことから「菜の花忌」と名付けられました。
Q: なぜ「菜の花忌」と呼ばれるのですか?
A: 司馬遼太郎は生前、特に春の菜の花畑の風景を愛し、その明るさや素朴さに惹かれていたと伝えられています。彼の命日である2月12日前後は、ちょうど菜の花が咲き始める季節でもあることから、彼の愛した花にちなんで、この名前で偲ぶようになりました。
Q: 司馬遼太郎はどのような作家でしたか?
A: 産経新聞社の記者を経て作家となり、膨大な資料調査と独自の史観に基づき、日本の歴史上の人物や出来事を生き生きと描いた歴史小説を数多く発表しました。その作品は「司馬史観」とも呼ばれ、多くの読者に歴史への興味を抱かせ、国民的な人気作家となりました。紀行文集『街道をゆく』シリーズも広く読まれています。