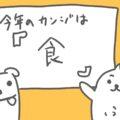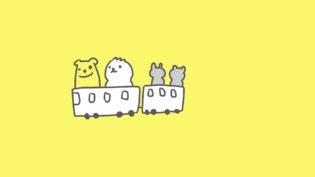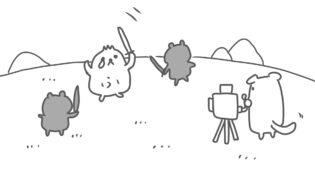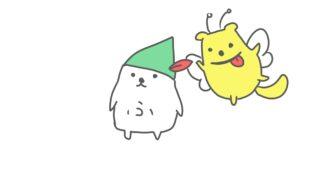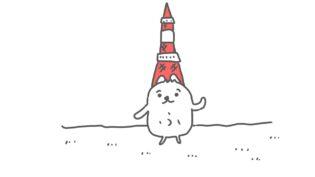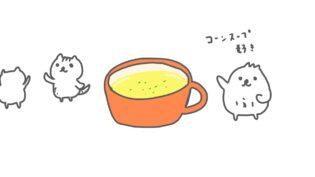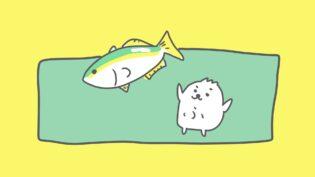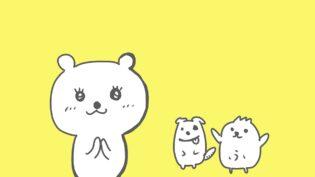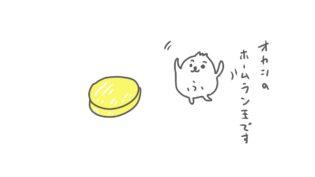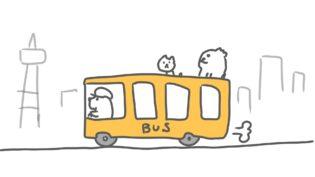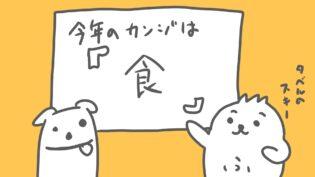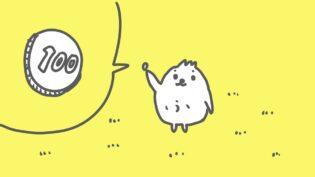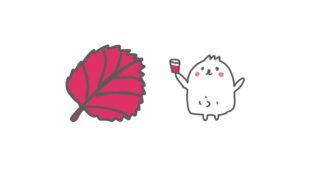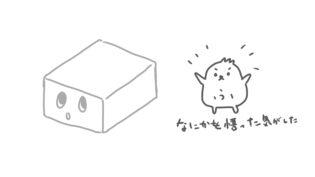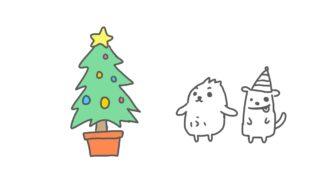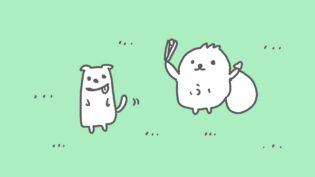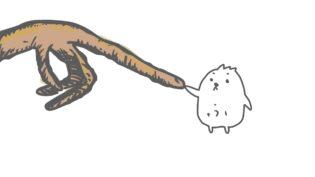12月13日は何の日?何の記念日?。簡単なエピソードとぽんぷーのイラストを添えてご紹介します。ちょっとした雑学ネタとして、何となく知ってたらいつか役に立つかも?
※面白い記念日が認定されたら追加していきます。
脚気治療の道を開いた発見: ビタミンの日
『ビタミンの日』制定委員会が制定。1910年(明治43年)12月13日に、日本の農芸化学者・鈴木梅太郎(すずき うめたろう)博士が、米糠(こめぬか)の中から脚気(かっけ)を予防する有効成分(後のビタミンB1)を抽出し、「オリザニン」と命名して東京化学会例会で発表したことを記念しています。
Q: ビタミンの日は、どのような出来事を記念していますか?
A: 鈴木梅太郎博士が、米糠から脚気に有効な成分(オリザニン=ビタミンB1)を世界で初めて発見し、その研究成果を発表した歴史的な日を記念しています。これは、ビタミンという栄養素の存在と重要性が科学的に認識されるきっかけとなりました。
Q: ビタミンという言葉は、誰が名付けましたか?
A: 鈴木博士の発見の翌年(1911年)、ポーランド出身の生化学者カジミェシュ・フンク(Casimir Funk)が、同様に米糠から脚気に有効な成分(アミン化合物)を分離し、生命(vita)に必要なアミン(amine)という意味で「ビタミン(vitamine、後にeが取れてvitamin)」と命名しました。オリザニンとほぼ同じ物質でした。
Q: ビタミンにはどのような役割がありますか?
A: ビタミンは、体の機能を正常に保つために不可欠な有機化合物ですが、体内でほとんど合成できないため、食物から摂取する必要があります。炭水化物、脂質、たんぱく質の代謝を助けたり、体の調子を整えたりする働きがあります。ビタミンA, B群, C, D, E, Kなど様々な種類があり、それぞれ異なる重要な役割を担っています。
年末の胃腸をいたわる「胃に(12)胃散(13)」: 「胃に胃散」の日
胃腸薬「太田胃散」を製造・販売する株式会社太田胃散が制定。日付は「胃に(12)いさん(13)」(胃に良い酸、または胃散)と読む語呂合わせから。忘年会シーズンで飲食の機会が増え、胃腸に負担がかかりやすい12月に、胃腸を大切にしてもらうことを目的としています。

Q: 「胃に胃酸」の日は、どのような目的で制定されましたか?
A: 忘年会など飲食の機会が多くなりがちな12月に、胃もたれや胸やけなどの胃腸の不調に注意を促し、胃腸をいたわることの大切さを啓発するために、胃腸薬メーカーである株式会社太田胃散が制定しました。
Q: なぜ12月13日が「胃に胃酸」の日なのですか?
A: 「胃に(12)胃散(13)」という、自社製品名を連想させつつ、胃の健康を気遣うメッセージを込めた語呂合わせから、この日が選ばれました。
Q: 忘年会シーズンに胃腸を守るための注意点は?
A: 食べ過ぎ・飲み過ぎを避けることが基本です。ゆっくりよく噛んで食べる、空腹での飲酒を避ける、アルコールと一緒に水も飲む、脂肪分の多い食事や刺激物を控える、などを心がけましょう。事前に胃腸薬を服用したり、食後に消化を助けるハーブティーなどを飲んだりするのも良いかもしれません。
師走の美の追求を応援: 美容室の日
美容師の正宗卓(まさむね たく)氏が2003年(平成15年)に提唱。日付は、美容室が最も忙しくなる12月であることと、数字の「13」を縦にして組み合わせると、アルファベットの「B」(Beautyの頭文字)に見えることから。
Q: 美容室の日は、どのような目的で制定されましたか?
A: 年末の繁忙期にあたるこの時期に、日頃美容室を利用している顧客への感謝の気持ちを表すとともに、美容師の技術やサービスの価値を社会にアピールし、美容業界全体の活性化を図ることを目的としています。
Q: なぜ12月13日が「美容室の日」なのですか?
A: 美容室が最も忙しくなる12月であることと、数字の「13」を組み合わせると「Beauty(美)」の頭文字「B」に見えるというユニークな見立てから、この日が選ばれました。
Q: 美容室でリフレッシュするコツは?
A: ヘアカットやカラー、パーマだけでなく、ヘッドスパやトリートメントなど、リラクゼーション効果の高いメニューを試してみるのもおすすめです。担当の美容師さんに髪の悩みや希望のスタイルをしっかり伝え、コミュニケーションを楽しむことも、満足度を高めるポイントです。
ふたご座流星群が極大に: ふたご座流星群の日
毎年12月13日から14日頃にかけて、三大流星群の一つである「ふたご座流星群」の活動が最も活発になる(極大を迎える)時期にあたります。空の条件が良ければ、一晩で多くの流れ星を見ることができる天体ショーとして知られています。(特定の記念日として制定されているわけではありませんが、天文ファンにとって注目の日です)
Q: ふたご座流星群とは何ですか?
A: 毎年12月上旬から中旬にかけて活動が見られる流星群です。放射点(流れ星が中心から放射状に流れるように見える点)がふたご座にあることからこの名前が付けられています。母天体(流星の元となる塵を放出した天体)は、小惑星ファエトンと考えられています。
Q: なぜこの時期に多くの流れ星が見えるのですか?
A: 地球が、小惑星ファエトンが過去に放出した塵(ちり)が漂う空間(ダストトレイル)の中を通過するためです。この塵が地球の大気に高速で突入し、発光する現象が流れ星として観測されます。特に12月13日~14日頃に、地球が最も塵の濃い部分を通過するため、活動がピーク(極大)を迎えます。
Q: 観察のポイントは?
A: 街灯など人工の光が少ない、空が広く見渡せる場所を選びましょう。目が暗闇に慣れるまで15分ほどは観察を続けるのがおすすめです。放射点を中心に空全体を眺めるようにすると、流れ星を見つけやすくなります。冬の夜は冷え込むので、十分な防寒対策が必要です。
一年の煤(すす)を払い清める日: 正月事始め・煤払いの日
昔、江戸城でこの日に煤払い(すすはらい:大掃除のこと)が行われていたことから、庶民の間でも12月13日を「正月事始め(しょうがつごとはじめ)」とし、お正月の準備を始める日とされてきました。特に、年神様(としがみさま)を迎えるために、家の内外を清める煤払い(大掃除)を中心に行います。
Q: なぜ12月13日が正月事始めなのですか?
A: 江戸城で年中行事として行われていた「煤払い」がこの日だったため、それに倣って庶民の間でもこの日を新年の準備を始める目安とする習慣が広まりました。
Q: 煤払いにはどのような意味がありますか?
A: 単なる大掃除という意味だけでなく、一年間に溜まった厄や穢れ(けがれ)を払い清め、清浄な状態で新しい年の神様(年神様)をお迎えするという、宗教的な意味合いも持っています。
Q: 正月事始めには他にどのような準備をしますか?
A: 煤払いの他に、門松にする松やおせち料理に使う薪などを山へ取りに行く「松迎え」などの準備も始められました。現代では、年賀状の準備を始めたり、お正月の飾り付けを考え始めたりする時期にあたります。