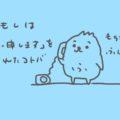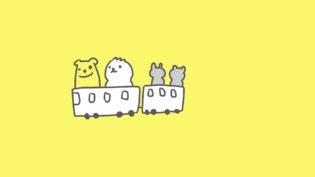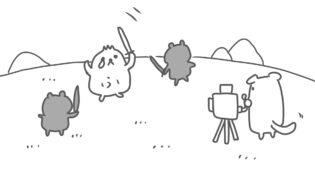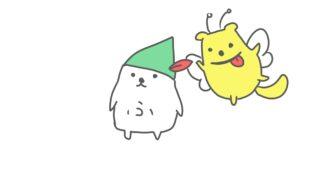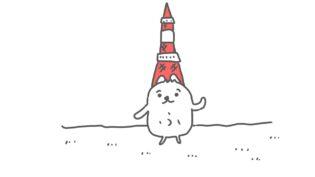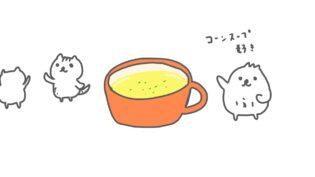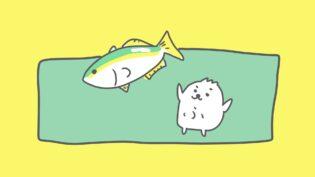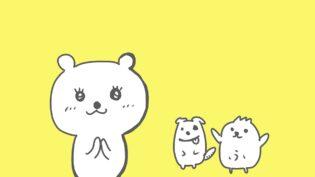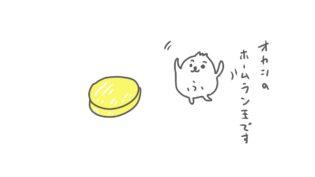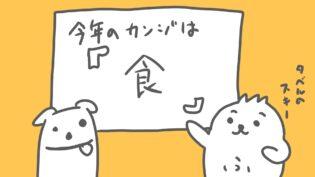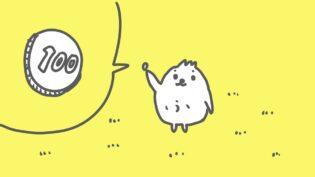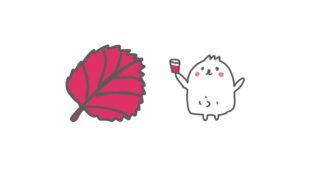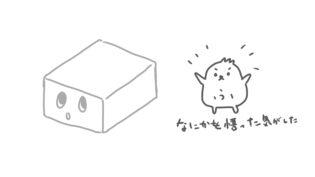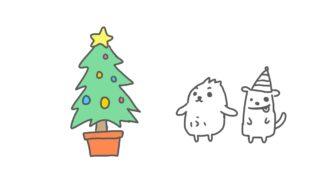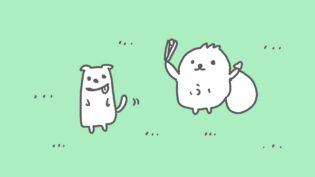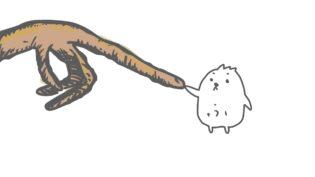12月15日は何の日?何の記念日?。簡単なエピソードとぽんぷーのイラストを添えてご紹介します。ちょっとした雑学ネタとして、何となく知ってたらいつか役に立つかも?
※面白い記念日が認定されたら追加していきます。
新年のご挨拶、元旦配達スタート!: 年賀郵便特別扱い開始日
毎年12月15日から、郵便局で年賀状(年賀はがき・年賀郵便)の特別扱いが開始されます。この日から12月25日までの間に投函された年賀状は、翌年の1月1日(元旦)に届けられるよう、郵便局内で他の郵便物とは区別して取り扱われます。
Q: 年賀郵便特別扱いは、いつから始まりましたか?
A: この制度が始まったのは1899年(明治32年)です。当初は東京などの一部の郵便局のみでの実施でしたが、好評だったため、1905年(明治38年)からは全国の郵便局で実施されるようになりました。
Q: 年賀状は、いつまでに投函すれば元旦に届きますか?
A: 12月15日から12月25日までの期間にポストへ投函すれば、原則として翌年の元旦に配達されます。ただし、宛先の地域や郵便事情によっては元旦に届かない場合もあります。早めの投函がおすすめです。
Q: なぜ年賀状を元旦に届ける特別扱いがあるのですか?
A: 新年の挨拶状である年賀状を、新年を迎える元旦に届けることで、お祝いの気持ちをより効果的に伝え、受け取る側にも喜んでもらうためです。年末の繁忙期に大量に差し出される年賀状を効率よく仕分けし、確実に元旦に配達するための特別な仕組みです。
東京見物をお手軽に!: 観光バス記念日
1925年(大正14年)12月15日に、東京遊覧乗合自動車株式会社によって、日本で初めての定期観光バス(路線バスではなく、名所を巡ることを目的としたバス)である「ユーランバス」の運行が開始されたことを記念する日です。

Q: 観光バスの日は、どのような出来事を記念していますか?
A: 日本初の定期観光バス「ユーランバス」が運行を開始し、バスによる観光という新しいレジャー形態が始まったことを記念しています。
Q: 最初の観光バス「ユーランバス」は、どのような場所を巡回しましたか?
A: 当時の東京の名所であった、皇居前広場、日比谷公園、銀座、上野公園、浅草観音(浅草寺)、明治神宮などを巡るコースだったようです。ガイド(案内嬢)も同乗していました。
Q: なぜ観光バスが運行されるようになったのですか?
A: 大正時代に入り、東京の都市化が進む中で、地方からの観光客や修学旅行生が増加しました。彼らが効率よく、快適に都内の名所を見学できるように、乗り合いバスを利用した定期的な観光ルートが考案されました。これが好評を博し、全国の観光地へ同様のバスが普及していくきっかけとなりました。
平和と人権を守る決意を新たに: 人権擁護委員の日
日本の人権擁護制度を支える「人権擁護委員」について、その制度や活動への理解を深める日です。日付は、人権擁護委員制度の根拠となる「人権擁護委員法」が施行された1949年(昭和24年)6月1日と関連付けられることが多いですが、具体的な記念日制定の経緯や12月15日とする明確な根拠は見当たりません。(※6月1日が人権擁護委員の日とされています)
Q: 人権擁護委員とはどのような人たちですか?
A: 法務大臣から委嘱を受けた民間のボランティアです。地域住民の中から、人格が高く、社会的な信望があり、人権擁護に理解のある人が選ばれます。全国の市町村に約14,000人が配置されています。
Q: 人権擁護委員はどのような活動をしていますか?
A: 地域住民からの人権に関する相談(差別、いじめ、虐待、ハラスメントなど)を受け付け、問題解決のための助言や、必要に応じて法務局への橋渡しを行います。また、人権思想を広めるための啓発活動(講演会、イベント、街頭キャンペーンなど)も重要な役割です。
Q: 人権相談はどのようにすればよいですか?
A: 全国の法務局・地方法務局に設置されている常設の相談所のほか、市町村役場などで開設される特設相談所でも相談できます。電話相談「みんなの人権110番」(0570-003-110)や、インターネットによる相談も可能です。相談は無料で、秘密は厳守されます。
冬の旬、濃厚な旨味を味わう: ザメンホフの日(生にしんの日)
ニシン(鰊)漁が盛んな北海道などで提唱されている記念日。日付は、冬に旬を迎えるニシンを「生」で味わうのに良い時期であることと、「生にしん」の「に(2)しん(15)」という語呂合わせから。特に、数の子の親としても知られるニシンの美味しさをPRする日です。(※注:ザメンホフの日は別由来の記念日です。この情報は「生にしんの日」として解釈します)
Q: 生にしんの日は、どのような目的で提唱されていますか?
A: かつては春告魚として大量に漁獲されたものの、資源量が減少し、近年また漁獲量が回復しつつあるニシンについて、その美味しさ、特に新鮮な「生にしん」の味わいを多くの人に知ってもらい、消費を促進することを目的としています。
Q: なぜ12月15日が「生にしんの日」なのですか?
A: ニシンが旬を迎える冬の時期であり、「生(なま)にしん(に=2、しん≒15?)」という語呂合わせから、この日が選ばれたと考えられます。(※語呂合わせとしては少し難しいかもしれません)
Q: ニシンはどのように食べるのが美味しいですか?
A: 新鮮な生にしんは、刺身や寿司ネタとして、脂の乗った濃厚な旨味を楽しめます。また、塩焼き、煮付け、フライ、マリネなども定番です。身欠きにしん(干物)を使ったにしんそばや甘露煮、そして卵である数の子も日本の食文化に欠かせない食材です。